
 大学生の「K」はUber Eats配達員、同じく大学生の「ICO」は人気Tik Toker――。現代の不条理に身を委ねながらも、前に進もうとするふたりの若者を描いた小説『K+ICO(ケープラスイコ)』(文藝春秋)は青春ものと呼べそうだが、描かれた若者像からは今を生きる息苦しさが見えてくる。そうした状況下でも「最善の振る舞いができる若者もいるのではないか」と作者の上田岳弘氏は語る。(聞き手=金澤英恵)
大学生の「K」はUber Eats配達員、同じく大学生の「ICO」は人気Tik Toker――。現代の不条理に身を委ねながらも、前に進もうとするふたりの若者を描いた小説『K+ICO(ケープラスイコ)』(文藝春秋)は青春ものと呼べそうだが、描かれた若者像からは今を生きる息苦しさが見えてくる。そうした状況下でも「最善の振る舞いができる若者もいるのではないか」と作者の上田岳弘氏は語る。(聞き手=金澤英恵)
「大きな物語」が壊れた今
――前作の『最愛の』(集英社)は恋人や家族といった「小さな物語」を取り戻すための大人の恋愛作品でした。続く最新作はUber Eats(ウーバーイーツ)配達員やTikToker(ティックトッカー、TikTok投稿者)として収入を得ている現代の若者が主人公です。私は主人公の「K」君が格好いいなあ、と思いましたが本作のテーマを教えていただけますか。
40代、30代の主人公は書いてきたので、若手、20代を書きたい、という気持ちがまずありました。Uber Eats配達員のKという主人公を設定して、あとは彼を外側から見て描いていきました。作品を書くときは、一種の自動筆記というか、浮かんできたことをどんどん文字にしていきます。はっきりしたテーマがあって書き出すわけではないのですが、書き終えて一冊にまとめてみてから振り返ると、「大きな物語」が消失した不条理な世界をどう生きるか、ということかと思います。
社会的ムーブメントという意味での「大きな物語」が消失した現代では、「こっちへ行けばいい」「こういう人を目指せばいい」というお手本となる存在がありません。昔は日本中が同じテレビ番組を見て熱狂していたけれど、今はテレビを見ない人も多い。しかも、社会的に影響力を持つ著名な団体や組織の不祥事がここ1年で次々と明るみに出て、大きな物語とそこから生まれた価値への信頼が共に崩れ始めている。
ただ、少なくない数の若者はこの状況を分析してではなく、予感していたのではないか。彼ら彼女らは大きな物語の価値なんてはなから信じていない。とはいえ、では自分が何を目指せばいいか、戸惑っている。

――「K」君は昨日より少しだけいい自分になることは望んでいるけれど、ギラギラした欲望のようなものは感じられず、確かに大きな物語の価値を信じていません。「K」君に出会う大学生の「ICO」ちゃんもそうですね。
そんな若者たちがいる一方、「K」が助ける「k」という少年の母親は40代、僕と同じです。僕らの世代は自分たちが信じて疑わなかった大きな物語や価値が崩壊していくさまを、今目の前に突きつけられている。
そもそも信じるものがない、はなから信じない世代。信じる大きなものがあった世代。それぞれが抱える不条理を描く。書き終えて自己分析するとこういうことかなあと。
――物語の中で、40代のサラリーマンたちが飲みながら「年上のおっさんたち」を責めつつ、「俺らも責任なしとは言えない。殴ってでも脅してでもおっさんたちのスクラムをやめさせて、正しい方向に持っていくことは論理的には可能だった。でも何もできなかった」と愚痴をこぼしているシーンがあります。なんだかすごくリアルな会話で同じ40代として身につまされました。
我々40代にとって、上司と部下、先輩と後輩、先生と生徒、そうした上下関係の権力勾配が明確でしたよね。その構造がかつての大きな物語に入っていた。
一方、大きな物語の構成員に加わっていない現代の若者たち、主人公の「K」は40代のサラリーマンたちとは真逆で、特定の世代や誰かを責めるといったような感情は抱いていません。
世界は支柱がなくなり「ぐにゃぐにゃの状態」になった。これはカフカが描いた不条理に近い印象がある。そこで今回、カフカの『城』(フランツ・カフカ著、前田敬作訳、新潮文庫)に登場する「K」をメインゲストとして召喚したわけです。

出来過ぎた主人公をあえて描いたわけ
――本作の「K」君は決して人に不快感を与えず、過干渉もせず、しかも誰かに求められたものを過不足なく差し出しています。若者の未熟さ、傍若無人さを感じさせません。
たしかに「K」の出来過ぎ感は否めません。とはいえ、ああいう行動をとりうるのではないかとも思うのです。情報技術が発展して、今はいろいろなものが見える。だからこそ、最善の振る舞いができる。情報技術がないとバイアスがかかり、勘違いがおきてしまう。
「K」は若いなりにいろいろなことを感じ取って自分の糧にしていく。人の動きや感情に対して反射的に最善の行動をとれる。あえて「K」の内面は描いていませんが。
そんな「K」は極悪とは対極にいて、本来なら物語になりづらいかもしれない。けれど今の時代なら最善であっても表現し得るのではないでしょうか。
実は「K」にはモデル、というかインスパイヤ源となる人物がいます。実在の著名な方で、モデルといっても彼は配達員をしていたわけではありません。カフカの城の「K」が彼だったら、どう行動するか、と想像して書いたわけです。「誰がモデル?」と謎解きをするつもりで読んでいただいても面白いかもしれません。
――もう一回読んで考えてみます……。SNS(交流サイト)で実際に炎上したUber Eatsの配達員を見下すような発言を引き合いに出すなど、本作では様々な偏見について描かれています。私事で恐縮ですけれども私は若いころ、予備校を途中で止めてフリーターになりコンビニエンスストアで働いていました。その間、誰かに「がんばっている?」と聞かれたことはありませんでした。見えない存在になってしまうというか、Uber Eatsをとりまく状況も似ている気がします。でも「K」君は人に見下されてもまったく気にしません。もちろん見下す側にも与しない。
Uber Eatsを生活が苦しい人が行きつく場所とか、ほかのところに行けなかった人がする仕事だとか、決めつけるのは一方的でしょう。自己選択として、Uber Eatsの配達員をしている人もいるはず。そういう人は見下されていようがいまいが関係ない、「K」のように。
また聞きなのですが、「すばるクリティーク賞」で選考委員をさせていただいた際に、Uber Eatsの配達員をしつつ批評を書いている方がいることを知りました。Uberの仕事は「楽しい」とおっしゃっているそうです。この話を聞くまえにすでに「K」の話を書き始めていたのですが、確証となる声を聞けました。
「正しさによって口をふさがれる」ことへの息苦しさ
――SNSの炎上の件、きっかけになった発言を私はリアルタイムで見ていました。著名な方が発信されていて驚きました。
社会から見たら強者に入る方がそのことに無自覚なまま、何か発言してしまい、「見下している」とたたかれることが結構ありますね。自分は強者と認識し、しかも自分が必ずしも正しいとは限らないと自覚して、それから発言したほうがいいわけですが難しいことでもある。
ただ、こうも思うのです。大きな物語を動かしていた権力者や強者が失墜し始めると「我々も実は恨んでいた」と無数の攻撃の矢が放たれる。本当にそれでいいのでしょうか。社会が総出で「オーバーキル」(過剰な攻撃)を行うことがいい結果を生み出すとは到底思えません。
民主主義はフランス革命から始まりましたが、民衆側で主導していた地方ブルジョワ階級出身のロベスピエールも結局は失墜し、味方であったはずの民衆の力で断首されてしまった。このところのオーバーキルを見ていると、その時代と変わらないと感じてしまいます。
――SNSで正しさを誇示する場面に出くわすことが増えました。「それは正しくない」という誰かの合図によって、対象人物があっという間に燃やし尽くされる。「オーバーキル」という表現通りと感じました。
僕が書いた戯曲『2020』(高橋一生氏の一人芝居として2022年に上演)に「君は正しさによって口をふさがれることになるよ」というセリフがあります。コロナ禍のトゥーマッチな自粛や過剰な抑制に対するアイロニーのつもりで書いたのです。
今になってみると、「正しさによって口をふさがれる」、これを現代社会で誰もが少なからず体感している。正しいことを言われる。正しいから反論できなくなる。そうした「正しさの濫用(らんよう)」のようなものが、オーバーキルにつながる。これはリスクをとって前に進むことへの抑圧になります。「そういう声が多い」と根拠に出されるとしんどい。
――K君やICOちゃんという清廉な2人と比べると、正しさで抑圧する側に回る人はなんだかご自身の実像が薄いですよね。
2人はささやかな手ごたえを得たわけですが、もっと大きな手ごたえがほしいという思いが人にはある。何をやっても何を言っても、世の中は自分の思うようには動いてはくれないし、身の回りの現実すら動かすのはままならない。けれども、いったん「正しい」とされた船に乗ることで、手ごたえがあり、日々の無力感から少しだけ癒やされる感じがするというか。
他人に自分の正しさを誇示する行為は無力感の裏返しみたいなところがある。オーバーキルを目にする機会が増えたのは多くの人が無力感にさいなまれているからかもしれない。それほど不条理な社会になってしまった、ということでしょうか。
Z世代も僕らも何も変わらない
――本作の主人公「K」君はUber Eats配達員、もう一人の主人公でTik Tokerの「ICO」ちゃんに、「Uber Eats配達員なんて、社会というシステムの末端の最たる例」と言われても、怒るでもなく「そういうこっちゃないんだよな」とつぶやきます。二人は同じ世代として通じる部分がありながらも、考え方は当初大きく違っていますよね。
主人公二人はいわゆるZ世代ですが、自我の守り方はそれぞれです。現代の若者はデジタルネーティブ世代ということもあり、対応しなければならないことが複雑怪奇になりすぎている。
もっとも40代の僕だって、この現代を若者として過ごしていたら、今のZ世代のようになっていたでしょう。若者が宇宙人に見えるとか、Z世代ひとくくりで偏見を持つ少し年上の人たちは、自分がかつて複雑怪奇な対応をする必要がなかったから、想像が及んでいないのかもしれません。
結局、人間は10万年前と何も変わっていない。僕たちは今も昔も変わらず、世の中や社会の空気に、その時々で必死に対応しているだけなのです。そういう意味では、サリンジャーの『 ライ麦畑でつかまえて 』(J.D.サリンジャー著、野崎 孝訳、白水社)は1951年の作品ですが、そこで描かれた「今の時代に、いかにして自我を守るか」という若者の課題は変わっていない。
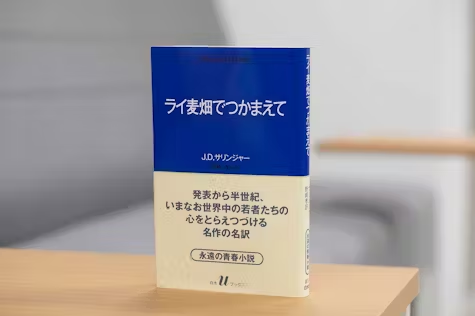
ただそうした中で、自我を守るあまり、何もせず、社会を自壊させてきた40代の姿も物語に差し込んでいます。僕の自責の念として入れたかったというのもあった。もうちょっと何かやりようがあったのではなかろうかと。
「日本終わった」はただの空気
――「この国はもう終わりだよ。もうなんにも残っていない」と、くだを巻く40代サラリーマンのセリフに今の壊れた社会の空気が漂っている気がしました。
「日本終わった」みたいな言葉を、近年はネットでよく目にしますよね。ただ、最近読んだ記事では、日本の経済成長率は先進7カ国(G7)でトップだと指摘されていました(「日本の経済成長率はG7トップ、この指標なら」〈ウォール・ストリート・ジャーナル、2024年1月2日〉)。
これまでは1人当たり国内総生産(GDP)を見て日本経済は停滞しているとされてきましたが、生産年齢人口(15〜64歳)1人当たりGDPで見た場合は、日本はトップの成長率になる。面白い調査結果だと感じませんか。
大学生でTik Tokerの「ICO」も、最初はインテリ大学生の元彼の影響もあって、今の社会は「搾取システムと末端の底辺で成り立っている」という考え方を持っていましたけれど、「そういうこっちゃないんだよな」とつぶやいた「K」の存在によって変わっていきます。空気に流されない、色々な物事を自分で冷静に見てみる。とても大切だと思います。
――世の中の絶望感や無力感になびいていた「ICO」ちゃんも、心の底では本心ではない、そんなことは思っていない、と自分でも否定しています。「ICO」ちゃんは苦学生でもあり、「誰かを見下さないとやってられなかった」という気持ちはよく分かりました。
「ICO」は学費や生活費をまかなうために、身体を武器にした動画をTikTokにアップしている。現代で生きるには最低水準の生活だけでなく、外観上も理想的な「普通」を装わなければならない背景があるからです。
外食費も物価も上がっている中で、僕ら40代が若者だったころの「普通」より、現代で「普通」を維持することは難易度が高い。とても大変そうに思える。けれども本作の「ICO」を通して、「普通の実装」みたいな苦悩を切り取りつつも、できるだけ希望的というか、前向きに自我を守っていく姿を描けたのではないかと。
「多数決」以外の正しさを測る物差し
――『K+ICO』は「みんながそう言っている」という空気に飲まれないようにするにはどうすればいいか、二人の若者を通して見えてくる作品でした。ちなみに、上田さんはこうした空気を変えていくために、どんなことが必要だと感じますか。
もともと民主主義が発生した理由は、力を持っていない人が力を携えて正しい方向に進むためでした。「王権」という絶対的な権力に抗い、民衆の意見を是とするために「一人一票」の力を拡大してきたのが民主主義だった。現代は「王権よりはマシ」になっただろうけれど、一人一票の力が以前より効力を発揮できていない。
それでも正しさを測る物差しとして「多数決」以外の方法を我々はまだ持ち合わせていません。SNSでも、フォロワー、リプライ、いいねの数といった、ある種の多数決によって、正しいか否かが判断されてしまう面がある。フォローやいいねをつけるに至った経緯は人それぞれで本来グラデーションがあるはずなのに。そのこと自体を問題として認識しないといけない。
「K」と対話を重ねる中で癒やされていった「ICO」のように、「これが正しい」といったん述べた人の意見でも変わっていくことがある。これからは多数決に変わる何らかの方法、もっというと「対話を排除しない社会の運用」みたいなものを、探していかないといけないのかもしれません。
――ところで全4章からなる『K+ICO』は文学界に連載された作品ですが毎回の掲載時期が結構空いていますね。
1章の「K」はもともと短編だったのです。短編の依頼があって書いた後、全体像がぼんやりと浮かび、2章3章4章、いずれも短編として発表する形で書き連ねていきました。全体を意識しながらも、そのつどソリッドに仕上げていくという書き方をしましたね。
――一気に読める半面、「K」君に呼びかける「姫」は誰なのか、とか、もう一人の「ICO」ちゃんは本当はどういう人なのか、とか、読後に疑問も残ります。
そのあたりは色々想像していただければ。ただ、別の作品で「ICO」のことは書くことになるような気がします。こちらは長編になるかもしれません。
 K+ICO
K+ICO
- 著者 : 上田 岳弘
- 出版 : 文藝春秋
- 価格 : 1,760円(税込み)
この書籍を購入する(ヘルプ): Amazon楽天ブックス
上田岳弘氏
(取材・文:金澤英恵、構成:谷島宣之、写真:小野さやか)
[日経BOOKプラス2024年2月9日、13日付記事を再構成]

|
最新記事、新刊、イベント情報をSNSやメールでお届けします 日経BOOKプラスの最新記事や「日経の本」の新刊、話題の本、著者イベントの予定など、ビジネスパーソンに役立つ情報をSNSやメールでお届けします。 https://bookplus.nikkei.com/atcl/info/mailsns/ |
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。






