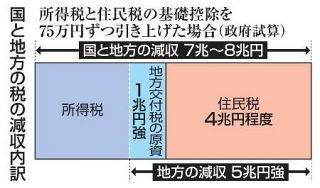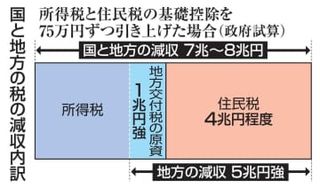焦点となった座礁船シエラ・マドレ
フィリピンの排他的経済水域(EEZ)内にあるセカンド・トーマス礁(フィリピン名アユンギン礁)が新たな南シナ海情勢の焦点となって久しく、日本政府や米国政府も「深刻な懸念」を表明してきた(※1)。同礁には、1999年にフィリピン政府がフィリピン海軍の輸送船BRPシエラ・マドレを座礁させ、海兵隊員を常駐させ監視拠点としてきた。ただし、座礁したシエラ・マドレだけで自給することは不可能で、外部からの定期的な補給と人員交代が必要となる。フィリピン海軍は、喫水の浅い船しか近づけない浅瀬を進んでシエラ・マドレに到達し、人員交代や必要物資の補給を続けるしかない。
こうした状況に対し、南シナ海で「歴史的権利」を主張する中国による妨害行為が続いている(※2)。2023年に耳目を集めた事案だけでも、中国の海警船によるフィリピン沿岸警備隊の巡視船に対するレーザー照射(2月)、同じく海警船による巡視船に対する放水銃の使用(8月)、海警船とフィリピン海軍のチャーターした補給船との衝突、続けて中国の民兵船とフィリピン巡視船との衝突(10月)、さらに海警船による放水と海警船と巡視船との衝突(12月)などがある。24年も状況は変わっておらず、フィリピン海軍が対応した際には、重傷者を出すに至った。一連の緊張状態の高まりが新しい常態であるかのようにさえみえる。
本稿では、このシエラ・マドレ補給をめぐる攻防の経緯を振り返りながら、海上における法の支配の促進についても考えていく。
ドゥテルテ時代も続いた中国の妨害行為
シエラ・マドレの補給作戦に関して、フィリピンと中国のどちらが事態を緊張させているのかという論戦が一部でみられる。フィリピンでは、2022年にドゥテルテ大統領が退任し、フェルディナンド・マルコス大統領が就任した。マルコス大統領は、就任以来、選挙戦当時のあいまいな態度から一変、対米関係強化に明確にかじを切っている(※3)。このことから、一部では、マルコス政権の積極的な対米接近が中国を刺激したという批判がある。
しかしながら、既に2010年代初頭には中国はシエラ・マドレへの補給作戦を妨害するようになった(※4)。そして、対中接近を図ったドゥテルテ大統領の時代にもそれは継続した(※5)。18年5月、中国人民解放軍海軍のヘリコプターが、フィリピン海軍のゴムボートに危険なほど接近した。ただし、この事案は、元海兵隊で当時国会議員であったギャリー・アレハノ氏が公表したもので、当時の外務省は問題を矮小(わいしょう)化しようと試みた。
アレハノ氏が、危険な行為でありいやがらせ(harassment)だと公表した後、アラン・ピーター・カエタノ外相は、偶発性をにおわせるような「事件」という表現を選んだ(※6)。ようやく19年9月になると、外務省ではなくフィリピン国防省が、少なくとも1隻の中国海警船がセカンド・トーマス礁付近に派遣され、しばしば補給作戦を妨害していることを公表した。21年11月には、中国の海警船2隻が、補給を試みたフィリピン海軍の木製ボートの航路を妨害、3隻目の海警船が放水銃を使用したため、ボートは補給を中断せざるを得なかった。その後、フィリピン政府は補給をあきらめることはないものの、中国側の妨害行為は継続してきた。
ドゥテルテ政権期の妨害行為の継続を考えれば、マルコス政権が事態を悪化させているという批判は根拠が薄弱、あるいは物事の順番が逆である。そもそも歴史をさかのぼれば、1995年に、中国は一方的にミスチーフ礁をフィリピンから奪い、その後は交渉で時間を稼ぎつつ、現状維持を約束しておきながら、99年にはミスチーフ礁の建物を堅牢化した。外交交渉が時間稼ぎに過ぎないのではないかと焦ったフィリピンの国防省が知恵を絞ったのが、シエラ・マドレを座礁させる作戦であり、ミスチーフ礁の強奪がなければ、シエラ・マドレ補給をめぐる対立さえ存在していなかったはずである。
南シナ海情勢を理解する上で、特定の時点に公にされている情報だけを切り取るのではなく、歴史的な経緯を理解する事の重要性が改めて浮き彫りになる。
問題を「見える化」したマルコス政権
それでは、なぜマルコス政権期に状況が悪化したように「見える」のだろうか。この疑問に対する答えは、マルコス政権が政策を変えたからである。ただし、ここでいう政策転換とは、対中接近から対米接近へという話ではない。南シナ海で起きていることについて、原則非公開から原則公開へと切り替えたことがより重要である。
一部の専門家が「積極的透明化作戦」と呼ぶように、マルコス政権は、南シナ海で起きた事象をほとんどリアルタイムで公表するようになった(※7)。その結果、世界中の人々が、フィリピンの排他的経済水域の中で中国が何をしているのか、いかに頻繁に嫌がらせをしているのかを理解するようになった。
もちろん、こうした情報公開は、情報収集を行う能力なしには実現不可能であり、この10年で進んだフィリピン海軍及び沿岸警備隊の能力強化が背景にある。これについては、2012年以来継続している軍近代化と、沿岸警備隊の能力強化が重要である。前者については米軍やオーストラリア軍との演習などを通じた協力、韓国やオーストラリア、インドネシア、日本といった友好国からの戦闘機を含む防衛装備品調達がある。後者については、米国政府による海上認識能力(MDA)強化を目指す協力と、日本の海上保安庁との協力が重要である。
これらの能力強化は、ベニグノ・アキノ政権が開始し、その後に親中姿勢を強めたドゥテルテ政権下でも継続してきた(※8)。マルコス政権は、過去10年の能力強化の果実を享受しているといえる。
エスカレーション避けるための警察比例の原則
南シナ海情勢に関してだれもが関心を持っているのは、果たしてフィリピンと中国の対立はエスカレートしてしまうのかという問題である。どの国も望んでいないとは思うが、フィリピン政府は間違いなくエスカレーションを望んでいない。その証左は、透明化作戦を担うのが沿岸警備隊であることにみてとれる。
2012年の中国公船とフィリピン公船との対峙(たいじ)の際、中国側は、自国の漁船に対してフィリピン政府が海軍所属の軍艦を派遣したことを批判した(※9)。その後、中国政府自身は海上法執行機関と海軍との区別があいまいになるような法整備を行ったのに対し、フィリピン政府は、軍と法執行機関の役割分担を前提として、沿岸警備隊の能力強化を図ってきた。
沿岸警備隊強化の一環として、フィリピン政府は、円借款を通じて日本から12隻の多目的船を調達、シエラ・マドレの補給作戦の最前線にも配備してきた。
日本政府のフィリピン沿岸警備隊に対する協力の特徴は、モノの供与にとどまらない点である。日本の海上保安庁は、既に1990年代から海上保安の分野で能力構築支援に関わっており、2000年代以降は、海賊や海上強盗を含む海上治安の分野にも協力対象を広げてきた(※10)。その際、強調されるのが警察比例の原則という実力行使をめぐる規範である。国際協力機構(JICA)で長く海上保安分野を総括した池田龍介氏は、「軍隊では敵対する相手を倒すための手段は問われませんが、PCG[フィリピン沿岸警備隊]には相手の抵抗の度合いに応じて必要最小限の権限を使うことが求められ」(※11)ると説明する。もともと、フィリピンの沿岸警備隊と日本の海上保安庁は、米沿岸警備隊をモデルとするなどの共通点もあり(※12)、日本の法執行分野での協力はフィリピンにとっても重要かつ受け入れやすい内容だったといえる。
海洋における法の支配を強化するのはだれか
海洋における法の支配の促進は、日本政府の自由で開かれたインド太平洋構想の柱の一つである。また、米政府もインド太平洋戦略を公表してきたことから、法の支配や国際法を強調するのは先進国、あるいは西側で、グローバルサウスはそうした規範を受入れないという主張がなされることがある。しかしながら、国連海洋法条約制定の歴史をさかのぼれば、海洋における法の支配を目指したのは、途上国側であった(※13)。同条約を制定するための長い交渉の過程で、フィリピンは、12カイリの領海という主張を、同盟国米国の反対をはねつけて主張した歴史がある(※14)。
海洋における法の支配を体現する国連海洋法条約は、西洋列強による力の支配を否定しようとした新興独立国の外交努力の結果でもあり、西側由来の規範というのは歴史的根拠のない主張である。歴史を踏まえれば、南シナ海問題において法の支配を重視するフィリピンの立場こそが、反「西側」の立場で、国際法を軽視する中国の立場が「西側」寄りとさえいえる。
いずれにせよ、フィリピン政府による沿岸警備隊を活用した情報開示は、まさに海洋における法の支配確立に向けた実践的な試みの一つである。シエラ・マドレ号補給をめぐる対立の経緯を正確に理解することは、南シナ海問題を超えて、海洋における法の支配の歴史を再確認することにつながる。南シナ海問題でフィリピンと協力することは、同盟国や有志国との連携強化ということに加え、海上における法の支配の促進という普遍的な目標とも真っすぐにつながっている。
(※1) ^ 飯田将史「南シナ海で進む日米比の安保協力―中国の強硬姿勢に対抗」Nippon.com、2024年5月13日
(※2) ^ 古谷健太郎「南シナ海における中国海警とフィリピン沿岸警備隊の衝突事件―フィリピンの対応と国際連携の重要性」笹川平和財団国際情報ネットワーク分析、2024年4月4日
(※3) ^ 高木佑輔「新興国フィリピンの外交:対米関係の強化、地域外交の深化と国際主義外交の展開」『国際問題』714号、2023年8月、pp. 6-16.
(※4) ^ Marites Vitug. Rock Solid: How the Philippines Won Its Maritime Case against China (Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2018), pp. 234-235.
(※5) ^ Marites Vitug and Camille Elemia. Unrequited Love: Duterte’s China Embrace. (Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2024), p. 152.
(※6) ^ Paterno R. Esmaquel II “China chopper harasses PH rubber boat in Ayungin Shoal – lawmaker” Rappler. May 30, 2018.
(※7) ^ Raymond Powell and Benjamin Goirigolzarri. 2023. “Game Changer: The Philippines’ Assertive Transparency Campaign: How the Philippines Rewrote the Counter Gray Zone Playbook in 2023” Stratbase ADRi Publications
(※8) ^ 高木佑輔「フィリピンの対中外交―交錯する3つのアクターと3つの政策」竹中治堅(編)『「強国」中国と対峙するインド太平洋諸国』(千倉書房 2022年)
(※9) ^ Jay Tristan Tarriela. The Rise of the White Hulls in Southeast Asia: The Philippine Coast Guard Case. (Ph.D. dissertation, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), 2020), pp. 53-55.
(※10) ^ Yusuke Takagi. “Philippines-Japan Maritime Cooperation in the Quest for a Rules-Based International Order” Philippines – Japan Relations in the Twenty First Century: Change and Direction, edited by Dennis D. Trinidad and Karl Cheng Chua (London: Routledge, Forthcoming).
(※11) ^ 「沿岸警備隊を強化してともに安全な海をつくる―フィリピン」『JICA Magazine』2023. no. 13., p. 21.
(※12) ^ Tarriela, The Rise of the White Hulls.
(※13) ^ 高林秀雄『国連海洋法条約の成果と課題』(東信堂、1996年)
(※14) ^ Alturo Tolentino. Voice of Dissent (Phoenix Pub. House, 1990)
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。