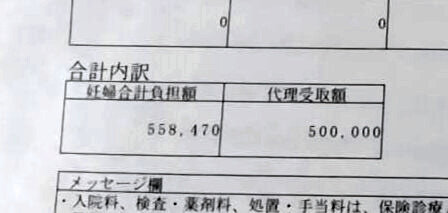中国の反面教師としてのソ連
川島 真 山田先生がアジア政経学会の理事長をなされた時期は冷戦が終結した直後ですが、その時期の世界、中国をどのように見ていらっしゃいましたか?
山田 辰雄 冷戦が終結して、私はたまたま個人的なことですけど、1990年の11月に東ベルリンにいました。そのとき人々は「壁」を壊していて、まさにそれに立ち会いました。冷戦が終結して、私は中国研究者ですから中国のことに言及しますけど、天安門事件後の中国はそろそろ立ち直り始めて、国際社会にも出ていこうとしていた時期でした。
アジアもだんだん変わっていきますけど、欧州とは異なって、冷戦が終結したからといって、そのことを契機にアジアが急激に変わることはなかった。むしろ中国はソ連の崩壊を反面教師として捉えていたと思います。それが鄧小平の改革開放につながっていくわけです。
ただ、冷戦が終わることでいわゆる社会主義圏とより容易に付き合えるようになったということはあります。私はその前から何回もソ連に行っていましたし、また東ベルリンのフンボルト大学とも関係が深かったので、何回かそこに行って会議に出たり講演したりしていました。だんだん冷戦が緩和する過程で、われわれの方からも社会主義圏に行きやすくなったと思います。

山田辰雄・慶応義塾大学名誉教授
天皇訪中と共産党政権
川島 1989年6月4日の天安門事件の後に西側がさまざまな制裁を中国に課していました。外交部長だった銭其琛の回顧録(※1)などを見ると、中国は天皇訪中を利用して自らを取り巻く制裁の輪を突破しようとする意図があったとも受け取れます。
山田 天皇陛下(現在の上皇陛下)は1992年に訪中されるわけですけど、その前に一応中国の話を聞きたいということで、文化人や学者を何人か呼ばれたのです。私はたまたまアジア政経学会の理事長だったものですから、学会代表で皇居へ行って天皇皇后両陛下とお話をしました。
私はそのとき一つだけ辛亥(しんがい)革命の話をして、日中の協力の観点からこの革命が新しい中国を生み出す上で非常に大きな意味をもっていたということに言及しました。その後何回か陛下にお会いする機会がありましたが、92年の訪中では、中国側は確か楊尚昆氏が接待に当たられ、天皇陛下はそのとき非常に良い印象をもたれたようです。楽しかったということと同時に、やはり中国はさすが歴史の国だということでした。接待を非常に礼儀正しくやってもらったということでした。
天皇陛下は、上海で非常に歓待されて、民衆の中を通っていかれた。そんな時代でした。確かに冷戦の終結という大きな変動がありましたけど、私の印象では世界や日本の変化が日本の学界のあり方に悪い影響を与えるというような状況ではなかったと思っています。
アジア研究と社会科学:政治による「普遍的」価値の利用
川島 中国近代政治史を研究してこられた山田先生から、現在の日本のアジア認識、中国認識などについて、メッセージをいただけますか。
山田 広い意味での社会科学におけるアジア研究の位置づけの問題があります。この問題意識を、私は以前から持っていました。それは、社会の歴史的発展と社会科学との関係という問題です。単純化して言いますと、ルネッサンス以来西洋の近代社会の発展があり、その発展の中で生まれた社会科学が、日本において、また世界において普遍的な理論体系として世界に広がってきました。
では、現代社会ではどうでしょうか。そこでは普遍的な価値を主張することによって逆に社会が分断されているという状態にあるのではないかと思うのです。つまり一方では人権だとか民主主義、他方では権威主義というような、本来学問的な意味での概念が現代社会では政治的に利用されて、世界が分断されているのではないかと私は考えています。
どういうことかと言いますと、近代においては西欧社会が非常に発展して強くなりました。そこで生まれた社会科学は、本来西欧的なものであるべきなのに、人権や民主主義とか、そういう形で普遍化されてしまってはいないか。そういう形で社会科学はアジアへも入ってきたわけです。しかし、20世紀後半にはアジア自体が政治的にも経済的にも発展してくるわけです。そうすると、その発展をどのように社会科学研究の中に相対化して取り入れるのかという問題が起こってきます。だから、このアジアの発展が、単なるアジアだけではなくて、社会科学の普遍的な原理の中にどのように組み込まれるのかということが、新しい社会科学の発展に結びついてくると思うのです。
アジア研究というのは、実は従来の社会科学をより高度化していくためのひとつの基礎的な研究であると私は考えています。その意味でアジア研究は、単なる西洋で生まれた社会科学理論のアジアへの適用ではなく、むしろ、アジアの現実の発展と従来の社会科学の理論との相互作用を通して、新しい社会科学の発展を目指さなくてはなりません。その意味で、アジア研究は社会科学の下にあるのではなくて、むしろ社会科学を発展させていくための資源であると思います。
現在の問題は、そのような普遍的とされる考え方が政治的に利用されて世界が分断されているということです。私は別に独裁体制がいいとは言っていません。そういう社会科学で生まれた普遍的な理論、普遍的な概念が政治的に利用されてしまっているということが、私の見方なのです。
社会科学の理論の背後にある「情念」
川島 欧米のアジア研究がそうした課題に気がつく契機はあったのでしょうか。
山田 ベトナム戦争がアメリカ中心的な考えに対し、ある種の疑問を投げかけました。そして、私は社会科学理論の背後にある「情念」に関心が向かいました。具体的にはマックス・ウェーバーとプリンストン大学の余英時(※2)の著作に私は興味をひかれました。実は社会科学者と言われている人たちの理論の背後には、情念、あるいはエートス、もしくは問題意識と言ってもいいものがあるのではないかと思うのです。マックス・ウェーバーの情念は、ヨーロッパの近代の資本主義の発展をいかに証明するか、いかにそれを正当化するのかということにあり、そこにプロテスタンティズムが用いられました。実は私は、ウェーバーを取り上げるのにプロテスタンティズムと同時に彼の儒教と道教の評価を並行して取り上げなくてはならないと考えています。ウェーバーはヨーロッパ資本主義の発展をいかに説明するかという情念に駆られていることが分かります。そこではどうしても儒教と道教は、近代化において下位に位置付けられています。
それでいいのか、ということです。19世紀だったらそれでいいかもしれませんが、20世紀になって中国、あるいは中国でなくてもアジアが発展してきました。むしろ、なぜアジアが発展してきたのか、アジアの自律的な発展とは何かを考えなくてはいけないのではないか。そういう意味で私は余英時の『中国近世の宗教倫理と商人精神』という著作に興味をもちました。余英時はかなりウェーバーを意識していますが、中国においては明清時代、16世紀以来、あるいはそこに至るまでに中国の倫理、宗教、仏教、道教、儒教が世俗化してくる過程を分析しています。この世俗化した宗教が、ある意味で台頭してきた商人階級のイデオロギー的な基礎になります。そこに余英時は、中国の自律的な発展を見い出そうとしている。私は彼の著作を読んで、そういう意味で感銘を受けました。
歴史学も含めての社会科学の発展の背後にはこういう情念があって、理論的な枠組みを生み出しています。そこまで見なければ、社会科学としてのアジア研究は浅くなるというか、成り立たなくなると思います。現在のアジア研究における動機づけ、あるいはその情念は何なのかということを、われわれは問わなければなりません。
 山田辰雄氏(左)と、聞き手の川島真・東大大学院教授
山田辰雄氏(左)と、聞き手の川島真・東大大学院教授
西洋の民主主義の根源/中国の権威主義的政治の根源
川島 現在、中国は世界第2位の経済大国に躍進しました。その中国をどう見るのかということが現在のアジア研究の中心的課題の一つになっているように感じますがいかがでしょうか。
山田 「中国といかに向き合うかというようなテーマ」は、政治的には意味があります。けれども、それが学問的にどういう意味があるのでしょう。どうも最近のアジア研究は、特に台頭する中国にどう向き合うのかという問題意識が先行していると思います。やはり現代のアジア研究は、そのような政治的な分断からもう少し自由になっていい。学問は政治ではないのだから、もう少し自由にやっていいと思います。
そうすると、分断された両方の社会がどうして生まれてきたのかということを、より客観的に分析してみる必要があるだろうと思います。つまり、西欧の民主主義が生まれてきた根源を探ると同時に、どうして中国とかその他の地域で権威主義的な政治や体制が生まれてくるのか。共通の価値観ではなくてそれらからより自由になって、なぜそういうものが生まれてくるのかということを客観的に分析することによって、われわれは社会レベルでの対話ができるのではないか。そこに社会科学あるいは世界の普遍的な価値というものをこれからわれわれは見出して、それを作り出していかなければならないのではないでしょうか。
私が見るところでは、現在、アジア研究があまりにも政治化されています。政治の問題と無関係ではありえないというのは分かりますけれども、学問はもう少し違った面で人間社会の自律的な発展に貢献できるのではないだろうかと思うのです。そういう意味では、学者はストイックになった方がいいと思います。
インタビューは、2022年9月26日、東京・虎ノ門のnippon.com で実施した。また、『アジア研究』(69巻3号、2023年7月)にインタビュー記録の全体が掲載されている。
(※1) ^ 銭其琛『外交十記』(世界知識出版社、2003年)、日本語訳は銭其琛著・濱本良一訳『銭其琛回顧録:中国外交20年の証言』(東洋書院、2006年)。
(※2) ^ 余英時(1930-2021)は天津生まれの中国史、思想史研究者。ハーバード大学で博士学位を取得後、ハーバード大学教授などを歴任、世界の中国史研究を牽引した。その著書『中国近世宗教倫理與商人精神』(聯経出版事業公司、1987年)は邦訳されている(余英時著・森紀子訳『中国近世の宗教倫理と商人精神』平凡社、1991年)。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。